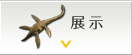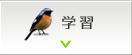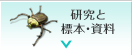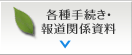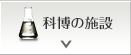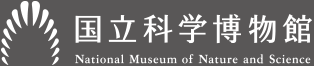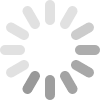
PC版はこちら
スマートフォン版はこちら

生命史研究部はヒトを含む地球上の全生命の成り立ちを理解するための標本・資料を研究対象としています。それらには、およそ35億年の歴史をもつ生物変遷史の記録となる多種多様な化石や、考古遺跡から発見された人骨標本や化石人類レプリカなどがあります。これらの資料について、3研究グループが分担して調査・研究するとともに、研究部を横断して学際的に取り組んでいる総合研究や特定のテーマに焦点をあてた重点研究も行なっています。また、これらの研究に伴って収集された標本・資料をデータベース化して、標本の研究・教育・展示への活用をはかっています。 |

展示中の恐竜アパトサウルスの実物骨格を解体して研究
古生物の系統分類、進化、古生物地理、古生態などの研究を行なっています。現スタッフは、ユーラシア大陸東部や南米の古植物地理と植生変遷、アジアや南北米大陸の中生代爬虫類の進化、古第三紀の大型哺乳類と新第三紀の小型哺乳類の系統、機能形態や古生態の進化、新生代爬虫類の系統進化と適応放散過程における行動様式、運動機能や感覚機能の進化、海生哺乳類の系統進化と適応放散などを研究テーマにしています。
収蔵資料は、地球上の生物の進化に関わる化石と関連資料を対象としており、現スタッフによる調査・研究や寄贈によって収集された標本を含む、約7万8千点が登録・保管され、研究・展示・教育に活用されています。収蔵資料の中には、分類同定の基準となるタイプ標本も多数含まれています。
地球環境の変動史と生態系の進化を研究しています。現スタッフは、太平洋や環太平洋の珪藻や有孔虫など微化石を用いた新生代海洋・湖沼環境の復元、巻貝・二枚貝類を用いた西太平洋域における種多様性の起源と変遷、頭足類を対象にした環太平洋地域の中生界層序と生物多様性変遷史などの研究を行っています。
収蔵資料は、環境変動や生態系に関わる化石と関連資料を対象としており、現スタッフによる調査・研究や寄贈によって収集された約16万2千点の登録標本が保管され、研究・展示・教育に活用されています。また、国際深海掘削計画で採取された微化石標本の共同利用センター(微古生物標本・資料センター: http://iodp.tamu.edu/curation/mrc.html)が置かれ、4万1千点の登録標本が研究に利用されています。

極東ロシア・沿海州での地質調査

採集された三畳紀のアンモナイト
 人類研究部では、人類の起源・進化および日本人とその関連諸地域集団の小進化・移住拡散過程を解明するため,あらゆる機会をとらえて標本資料を収集し,形態学的・分子人類学的な研究を行なっています。収集・管理している標本の大部分は日本の縄文時代から江戸時代までの古人骨であり、内外の研究者に広く利用されています。
人類研究部では、人類の起源・進化および日本人とその関連諸地域集団の小進化・移住拡散過程を解明するため,あらゆる機会をとらえて標本資料を収集し,形態学的・分子人類学的な研究を行なっています。収集・管理している標本の大部分は日本の縄文時代から江戸時代までの古人骨であり、内外の研究者に広く利用されています。
当館では各研究分野特有の基盤研究と分野横断的な総合研究を実施していますが、人類研究部職員は、現在、各人の専門性を活かしつつ、当館の中期計画に盛り込まれた基盤研究を行なうと同時に総合研究にも貢献しています。具体的な人類研究部職員の専門性は以下のとおりです。
その他、他研究部と横断的に取り組んでいる総合研究や特定のテーマに焦点をあてた重点研究をおこなっています。
詳しくは、総合研究をご覧ください。