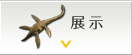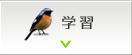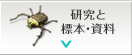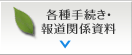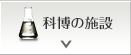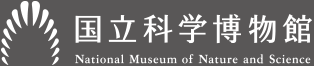| ホーム ≫ 利用案内・情報 ≫ ホットニュース ≫ 2009-05-15 |

2009-05-15
目が離せない恐竜発掘・研究事情(協力:地学研究部 冨田幸光,真鍋真)
恐竜の子育て:卵を抱くオスがいた?
 現生の鳥類では卵やヒナの世話に,オスの協力が必要な場合が多いことは良く知られています。実に9割以上の種で,オスが卵を温めたり,餌を取りに行ったりと育児に協力しています。哺乳類では5%未満,爬虫類や両生類などではほとんどが産みっぱなしか,メスだけが世話をしていることを考えると驚くべき比率です。
現生の鳥類では卵やヒナの世話に,オスの協力が必要な場合が多いことは良く知られています。実に9割以上の種で,オスが卵を温めたり,餌を取りに行ったりと育児に協力しています。哺乳類では5%未満,爬虫類や両生類などではほとんどが産みっぱなしか,メスだけが世話をしていることを考えると驚くべき比率です。この「オスによる子育て」が,鳥類の祖先とされる小型獣脚類の恐竜で既に始まっていたとする研究が,昨年12月,アメリカの科学誌『Science』に発表されました。
白亜紀後期の北半球に生息していた小型の獣脚類,トロオドン類(※4)は,非対称な形,層状の殻など,現生の鳥と良く似た特徴を持つ卵を産んでいました。卵の並んだ巣の化石と一緒に,卵の世話をしていたらしいおとなの化石もしばしば発見されてきました。
恐竜の化石からオス,メスを直接判定することは簡単ではありません。生殖器など性別を明確に示す組織は,化石として残りにくいためです。
現生の鳥や爬虫類は,卵の殻に,カルシウムとリンを多く含んでいます。鳥類のメスでは産卵期になると,大腿骨の内側に「骨髄骨」とよばれる特別な構造がつくられ,そこから殻の原料となるカルシウムやリンが供給されます。ワニなどの爬虫類のメスではこの骨髄骨が作られないため,骨そのものからカルシウムやリンが溶け出してしまいます。
2005年,アメリカでティラノサウルスの大腿骨(次ページでご紹介している,タンパク質が保存されていたとされるティラノサウルスと同一の標本です)の化石から骨髄骨が発見され,この個体が産卵期のメスであったと判ったことがありました。
そこで今回も,卵を抱いた状態で見つかった恐竜たちの後足の骨の内部構造が調べられましたが,骨髄骨は発見されませんでした。骨から直接カルシウムなどが溶け出したらしい様子も見られませんでした。
自分の体内のカルシウムやリンを使わずに卵を産もうとする場合,カルシウムやリンを多く含む餌を採ることによって身体の外から補給するしかありません。しかしこの方法では大きな卵を幾つも産み続けることは難しいでしょう。
このことから,卵を抱いていた親はメスではなかった可能性が高いと言えます。
また,現生の鳥では,親が1度にあたためる卵の総容量(大きさ×数)を,おとなの体重がほぼ同じ種同士で比較した場合,オスだけが育児を行う種で容量が最も大きくなり,両親が育児を行う種で最も小さくなることが知られています。
オスに育児を任せられる場合メスはより大きく,たくさんの卵を産むことに集中でき,逆に両親が一緒に子育てを行う場合,卵にかかる体力の消耗を抑えることで,ヒナの世話の方により多くの時間やエネルギーを使うことができるためと考えられています。
トロオドン類の恐竜では,巣の中で発見された卵の数は20~30個と多く,卵の大きさも親の身体に比べて大きなもので,現生の鳥のうちダチョウやレア,エミューなど,オスだけが子育てをする種の卵の総容量に極めて近いものだったことが判りました。
骨の構造,卵の総容量共に状況証拠のため,本当にオスが卵を抱いていたと結論づけるにはまだ早いかもしれません。オスだったとしてもトロオドン類に限った話で,他の恐竜ではメスが卵を抱いていたかもしれません。
しかし,恐竜を含め爬虫類,鳥類の子育ての起源については判っていないことが多く,今回の成果は非常に興味深いものです。羽毛や飛行能力の獲得など,恐竜が「鳥らしく」なっていく過程を知る上でも面白い1歩と言え,今後の発展を見守っていきたいところです。
※4 トロオドン類…プロトケラトプスのものと思われた卵の入った巣の上で発見されたことから,卵を盗って食べようとしていたとして「卵泥棒」を意味する名前をつけられた,オヴィラプトルなどが含まれます。後にその卵はオヴィラプトル自身のものだったとわかり,泥棒の汚名は返上されましたが,学名は変更が許されないため,今もオヴィラプトルのままです。
図:現生鳥類・ワニ・恐竜の体重と巣の卵の総容量の関係
Varricchio et al., Science Vol.322, 1826-1828(2008)より改変